
坐禅|足の組み方

坐禅の組み方には2種類あります。
結跏趺坐(けっかふざ)と半跏趺坐(はんかふざ)です。
 結跏趺坐…右の足を左の腿の上に深くのせ、次に左の足を右の腿の上にのせます。
結跏趺坐…右の足を左の腿の上に深くのせ、次に左の足を右の腿の上にのせます。

半跏趺坐…右の足を左の腿の下に深く入れ、左の足を右の腿の上に深くのせます。
結跏趺坐は、坐禅の最も基本的な坐法であり、お釈迦様が悟りを開いた時の坐り方 と言われています。
しかし、初心者や体が硬い方にとっては、この坐り方は難しく、結跏趺坐ができないという方も少なくありません。

結跏趺坐をするには、股関節や足首、膝などの関節の柔軟性が必要です。
現代人は椅子生活が当たり前で、デスクワーク、スマホなどで長時間座ったり曲げたりしていることで、関節や筋肉が硬くなったり衰えたりしています。
そのため、結跏趺坐をすると痛みや違和感を感じたり、しびれたりしてしまいます。

痛みや違和感を感じたり、しびれたりしては 拷問の坐法 になってしまいます。
半跏趺坐(はんかふざ)でしたら、片方の足の上にもう片方の足をのせるだけでありますので、出来ることから始めてみて下さい。
また、いつでも どこでも 誰でも 気軽にできる いす坐禅 があります。

近年、足を組むことが難しいという人が増えています。
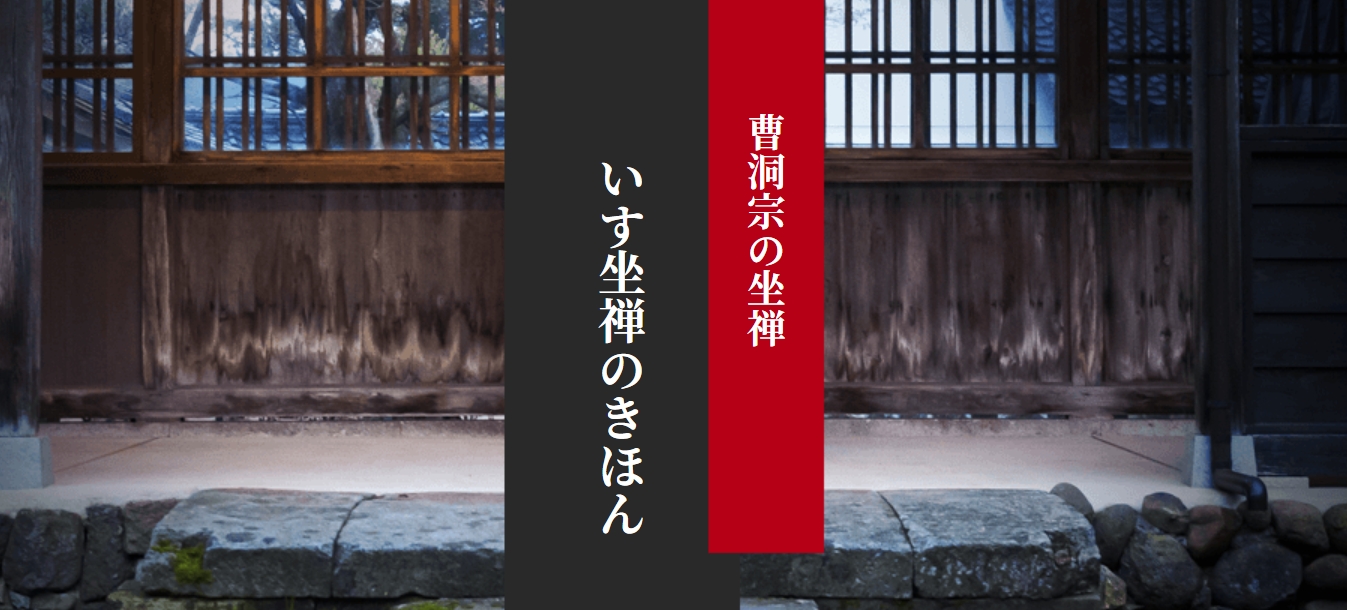
そうした方々でも、いす坐禅 は通常の坐禅と同じく 身・息・心の調和 を味わうことができます。

曹洞宗の教えの根幹は 坐禅 にあります。
それはお釈迦さまが坐禅の修行に精進され、悟りを開かれたことに由来するものです。
禅とは物事の真実の姿、あり方を見極めて、これに正しく対応していく心のはたらきを調えることを指します。
そして坐ることによって身体を安定させ心を集中させることでで身・息・心の調和をはかります。
皆様、機会がございましたら是非、坐禅 にご参加下さい!




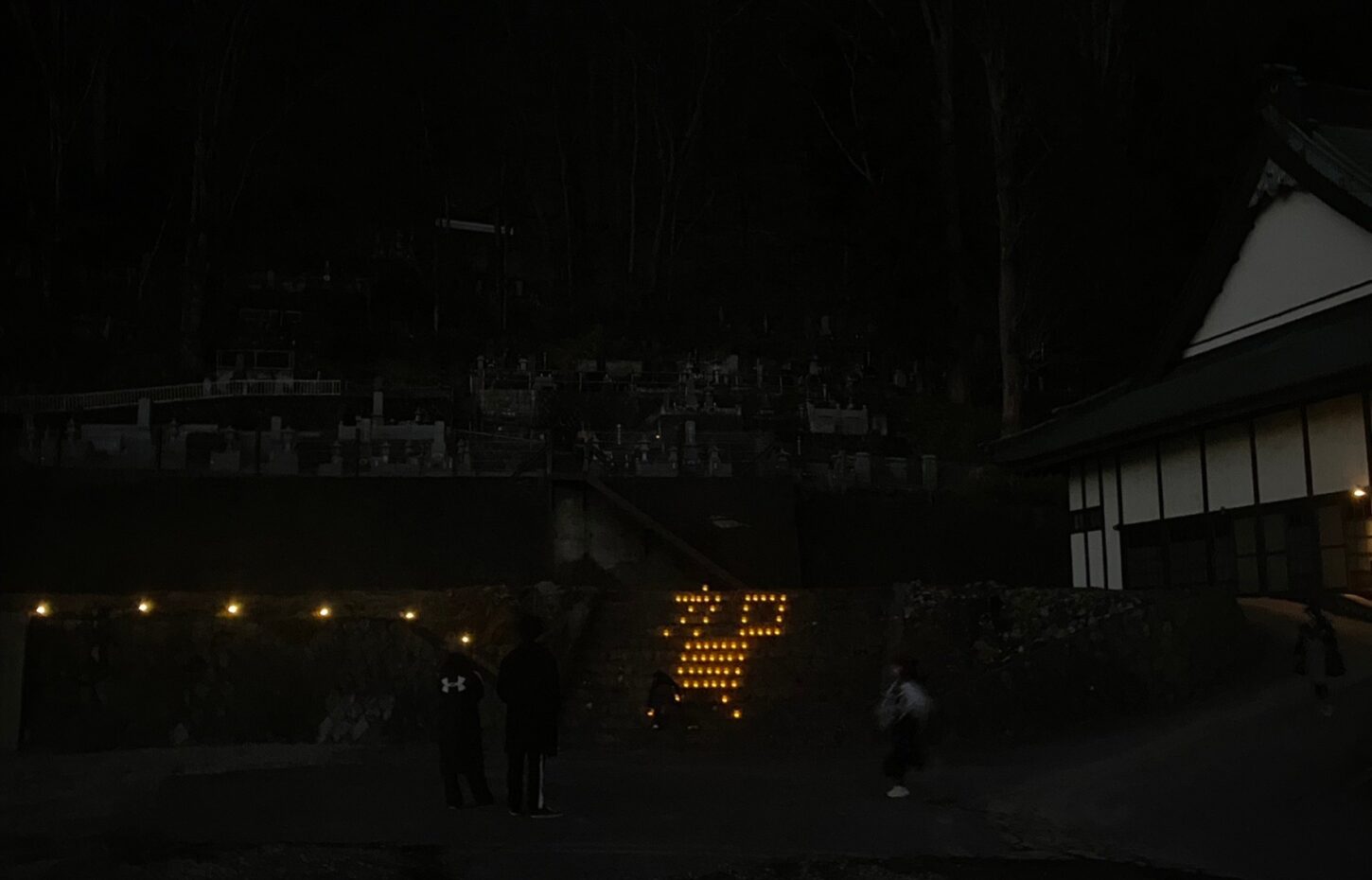


この記事へのコメントはありません。